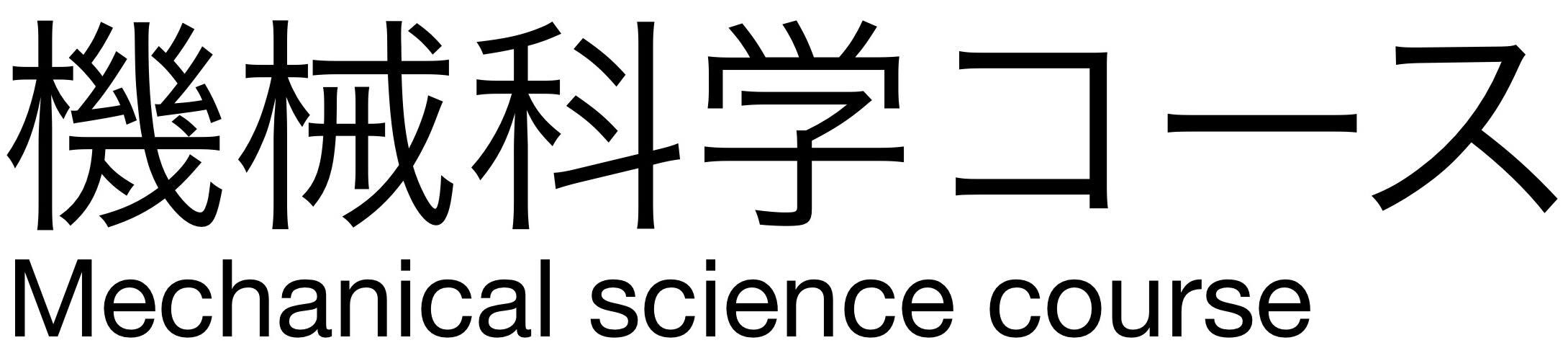空力騒音解析
背景・目的
自動車や航空機などの輸送機関やコンピュータやエアコンなどの工業製品から発生する騒音が問題になっています. 製品開発をする際には低騒音化が求められています。本研究室では数値解析を用いて空力騒音の発生原因や低騒音化技術の開発に取り組んでいます.
研究内容
騒音の制御技術の開発
生態模倣について
生体模倣とは、生物の構造や機能、生産プロセスを観察、分析し、そこから着想を得て新しい技術の開発や物造りに活かす科学技術のことです。 蚊の針に学んだ極細の痛くない注射針、ヤモリの指に生えている繊毛にヒントを得たヤモリテープ、ハスの葉の超撥水性を応用した塗料、サメの肌の特徴を模倣することで水の抵抗を低減した水着 、蛾の眼(モスアイ)を模倣し光を反射しない微細構造を持たせたフィルムなど、例を挙げればきりがないほど様々な技術開発や物造りに物生体模倣は活用されてきました。


生体模倣による翼後縁騒音の低減化に関する研究
航空機の翼から発生する空力騒音が問題になっています。飛行時の騒音は、翼後縁に発生する空気の渦が原因だと知られており、翼の形状を変化させることでの改善が進んでいます。しかし、現状は騒音抑制のみに着目した研究が多く、空力性能との両立に関しての研究は不十分です。そこで、本研究ではゼニガタアザラシのひげの形状に着目しました。ゼニガタアザラシのひげは表面が波打っている効果により、カルマン渦を抑制する効果があることが分かっています。なので、ゼニガタアザラシのひげの形状を翼後縁形状へ生体模倣することで翼後縁騒音の低減化につながると考えました。 流れ場と音響場の数値解析には格子ボルツマン法(LBM)を用いて同時計算を実施し、翼後縁騒音に及ぼす後縁形状の影響について調査し、最終的には騒音抑制と空力性能を両立させる新しい翼後縁形状の開発を目指しています。


ドローンについて
ドローンとは、人が乗車せずに遠隔操作で動く飛行機のことです。現在、ドローンは様々な場面で使用されています。 例としては、宅配ドローンや3次元測量、インフラ点検、人が行けない場所での災害調査、生育調査などの精密農業、漁場探索などです。 さらに、将来的には消火活動や高所危険作業などへの応用も期待されています。このように様々な分野で活用され始めたドローンですが、運用するにあたっての問題点がいくつかあります。 問題点の一つとして騒音問題が挙げられます。ドローンが飛行するとき「ブーン」という音がプロペラから聞こえてきますが、この音がドローンの騒音問題の原因となります。


ドローンプロペラの空力特性および空力騒音の数値解析
ドローンの爆発的普及により、騒音問題への発展が懸念されています。ドローンによる騒音は、プロペラの翼端に発生する渦が主な騒音源になっていると考えられています。 本研究では格子ボルツマン法を用いてドローンプロペラまわりの流れ場と音場の直接解析を実施するこで、実験で得られる結果に近い解析を行います。 この手法による流れ場の予測精度の向上によりドローンによる騒音の原理がさらに詳しく解析されることが期待されます。

ファンについて
ファンとは、羽根車を回転させて風を送り出す装置のことで送風機とも言います。機械換気をするための装置であり、空調風を室内に送り出す「空調機」や冷却熱を外部に送り出す「冷却塔」などの構成部品にもなっていて様々な機械に取り付けられています。 羽根車は、複数のプロペラを取り付けた部品です。電動機の回転エネルギーを主軸を通して送風機の内部にある羽根車に伝えることで、送風を発生させます。 送風機の最も重要な部品であり羽根車の形状により、送風機の種類が、遠心送風機、軸流送風機、斜流送風機、横流送風機の4つに分類されます。


流体性能の高精度予測
自動車や航空機などの輸送機関、コンピュータやエアコンなどの電子機器・家電製品など様々な工業製品で空力騒音が問題となっており、空力騒音低減手法の開発が製品開発における主要課題となっています。 本研究では、ファンの空力騒音低減化を目指し、流れ場と音響場とを同時に解析する直接計算を可能とする格子ボルツマン法(LBM)を用いてプロペラファンの流れ場の解析を行い、生み出される騒音を音響スペクトルとして異なる流量係数ごとに比較しました。